少し前に、休暇で沖縄へ行ってきました。
日々のルーティンが何も無い状態に放り込まれると、普段の場所やマインドでは見えなかったことに気づくことがあります。

外食が続いて気づいたこと
小さい子供がいると、本人が希望したメニューでも、
(多分食べられないだろうな…)
(かなり量が多いから、残すだろうなぁ)
と感じることがあります。
旅行中、私は子どもが残した分も多少食べることを想定して自分の注文をしていました。
でも、思っていたより子どもがしっかり食べて全然残らなかったり、私が注文したものを欲しがったりして、私自身が食べたかったメニューが充分に食べられなかったり、逆に残ったものを食べ過ぎたりしてしまい…
どんなお店に行っても、いつも何となく中途半端、満足感が薄い食事体験になっていることに気づきました。
なぜ残せない?&自分の好きなものを思い切り頼めない?
食べ物を残すのは勿体ない、という庶民的な感覚が原因と言えばそれまでなのですが、
「なぜ食事を残せないのだろう?」
「どうして、自分の好きなものを充分に自分に与えることが出来ないのだろう?」
と思って振り返ってみると
☆料理を残して、作ってくれた人をがっかりさせたくない。
☆食べ物を残すのは悪いことだという信念がある。だから残すことに罪悪感がある。
と、尤もらしい理由が出てきました。
一見美徳だし、正しいように感じました。
でもその信念に従うには、子どもが残す分にも責任を持たなくちゃいけない。
自分が食べたい料理を好きなだけ食べたら、正しいこと(子どもの残飯処理)ができなくなっちゃう。
だから我慢しなくちゃいけない、満足できる食事はできない…
そんな風に罪悪感で自分を縛って、好きなように食事を楽しむことを自分に許せずにいたのでした。外側にある窮屈な正しさの枠に、無理やり自分をはめようとして苦しくなる、我慢させる…これまで何度も経験してきた、あの嫌な感じ。
子どもが残してもいいよう、側でスタンバイしているような食事の時間は嫌なものだし、そもそも食べ残しを食べるって衛生的に問題があります(子どもの風邪を貰ったりすることもある)。
そして何よりも、自分の喜びが他の人の行動(むら気のある子どもの食欲)次第という、自由がない状態が嫌だなと感じました。
そうじゃないよね。
周りの環境次第で幸せになれるかどうかが決まるんじゃない。私は誰に頼らなくても自分で幸せに居られる。そう決めたのでした。
そもそもお店で出てくる量と、人が食べたい量がぴったり同じなんてことは、難しいです。大人だって、意外と多くて食べられなかったなんて時もあるから。
自分の欲求を我慢して、周りに合わせた中途半端な状態での「ごちそうさま…」と、食べたいものを満足に食べたあとの「ごちそうさま♡」は、全く別のものだと思います。
作ってくれた人に心から感謝するためにも、まず自分が満たされることを意図しよう。遠慮せずに食べたいものを選んで、満足する量は自分で決めよう。
旅行の途中でそう決めました。
「残さないこと」よりも、「私は今これが食べたい」とか、「自分はこれで満足、ここで終わるのが幸せ」というラインが感覚としてちゃんと分かるということの方が、生きる上で大切じゃないかなと思います。
(※フードロス運動を否定はしていません。「残さないことが何より大切」なのでは無く、あくまでも自分や相手、食物に愛を持って主体的に取り組むのが大事なのであって、我慢したり罪悪感で自分を苦しめながらやるものではないと私は思っています。)
言語化が難しいですが、なにかが伝わったらとても嬉しく思います
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
それではまた🌈

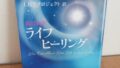
コメント